

不正咬合の種類
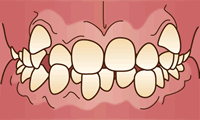
日本人に最も多い不正咬合で、八重歯も叢生の一種です。顎の大きさに対し歯が大きい事が原因で、歯が重なり合ったり凸凹になっている状態です。
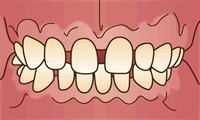
いわゆる「すきっ歯」の状態で、歯の大きさが小さかったり歯の欠損が原因で起こります。
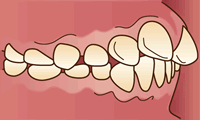
いわゆる「出っ歯」の状態で、上の前歯や上あごが前方に突き出しているため、お口が閉じづらくなることが多いです。
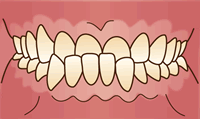
いわゆる「受け口」の状態で、前歯が反対に咬んでいます。下の歯が上の歯よりも前に出ています。
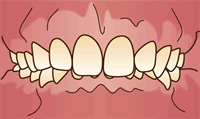
上の前歯が過度に下の前歯に咬み込んだ、いわゆる咬み合わせが深い状態です。上の前歯は下の前歯に対し2.0~3.0mm程度重なるのが通常です。
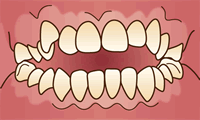
奥歯は咬んでいるのに、上下の前歯が咬み合っていない状態です。口呼吸になりやすいです。
お電話もしくはオンラインからご予約ください。
まずは、歯並びや口元で一番気になるところやお悩みをうかがいます。その上でお口の中を拝見し、矯正治療の流れや費用、予想される治療期間について簡単に説明いたします。この段階で矯正治療を始めるかを決定していただく必要はありません。
正しいかみ合わせときれいな歯並び、理想的な横顔を得るための診断資料として、矯正用のレントゲン撮影や歯型、お口の中やお顔の写真などをとらせていただきます。
検査結果から現在の問題点を抽出し、当院で提供できる治療方針と治療計画をご提示いたします。そして治療法と予想される治療期間また、安心して治療を受けていただけるよう、費用やお支払い方法についてもご説明いたします。
当日、ご希望があれば装置装着の準備を行うことも可能です。
矯正治療をご希望される場合は矯正装置装着の準備(型取り等)を行います。
いよいよ矯正装置を装着します。所要時間は装置の種類によって異なります。装置装着後は、装置の特徴とその注意点について詳しく説明します。
4週から8週に1度の間隔で来院していただき、矯正装置の調整を行います。
| Ⅰ期治療(子供の矯正治療) | Ⅱ期治療(大人の矯正治療) |
| 混合歯列期(乳歯と永久歯が混在) | 永久歯列期(全て永久歯に交換) |
| 6歳~12歳頃 | 12歳頃~ |
「しもつけ矯正歯科」では子供のうちから
歯列矯正を始められることをお勧めいたします
男女差(女児の方が早い)、個人差もありますが、上あごの成長は7~9歳頃にピークを迎え、その後、下あごの成長のピークが訪れます。そのため成長を妨げる要素(歯並び、習癖等)を取り除いたり、逆に成長を利用することで理想的な顔貌に近づけたり、大人になってから歯を抜かずに治療ができる場合があります。
通院間隔はおよそ1ヶ月〜2ヶ月に1回の割合で、治療期間は2~3年ほどです。
装置をつけて歯を移動させ歯並びと咬み合わせを整える治療です。
大人になってからでも遅くありません。
非常にシビアなケースでは、成長期のⅠ期治療で上あご、下あごのバランスや大きさを整え、成長が終了し永久歯が生え揃ったⅡ期治療で残された問題に対し歯の移動で修正を図る2段階治療を行うこともあります。
顎の成長は終了しているため、歯の移動範囲に制限はありますが、大人は自らの意志で治療を始めるため子供の矯正と比べ効率よく治療が進みます。お口の健康状態に問題がなければ、何歳になっても開始することができます。お気軽にご相談ください。
通院間隔はおよそ1ヶ月に1回の割合で、治療期間は2~3年ほどです。また、治療後の後戻りを防ぎ歯並びを安定化を図る保定期間は2年で、この間の通院間隔は3ヶ月に1回程度です。
歯の表側に「ブラケット」と呼ばれる装置を取り付け、そこにワイヤーを通して歯を少しずつ正しい位置に動かしていく矯正治療法です。目立たなくするために歯の色に近い白色のブラケットとワイヤーを使用し、審美面においても十分配慮しています。当院では従来型のブラケットと比較して摩擦抵抗が少ない「セルフライゲーションブラケット」使用しており、より小さな矯正力でスムーズに歯の移動が行えます。
ブラケットやワイヤーを歯の裏側(舌側)に装着する方法です。当医院では、既製品ではなくブラケットから完全オーダーメイドで作製する装置を使用しているため、装置の厚みを減少でき、より快適に矯正装置を装着できます。
透明なマウスピースを2週間に一度交換して歯を動かす装置です。他の治療法と異なり、装置の取り外しが可能です。また、プラスチックでできているため金属アレルギーの心配もありません。ただし、1日20時間以上の使用が必要です。
それぞれの矯正方法にはメリット・デメリットがあり、最善の治療方法はお口の中の状態によっても異なります。まずはご相談下さい。
矯正歯科治療は公的医療保険の適用外の自費(自由)診療となります。
※表示されている費用は税込です
矯正歯科治療に関する費用は医療費控除の対象となる場合があります。
矯正歯科治療に関わる領収書は、ご自宅で大切に保管してください。
詳しくはお近くの税務署または国税庁のHPでお調べください。